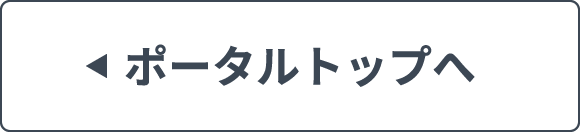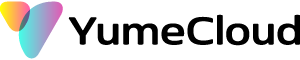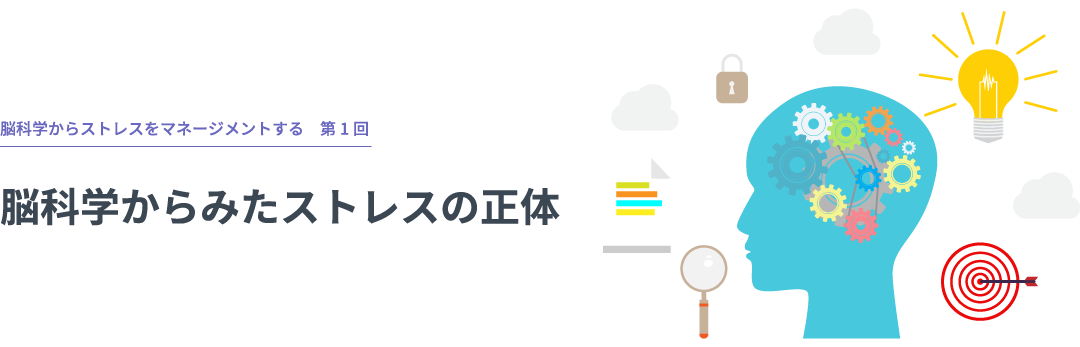
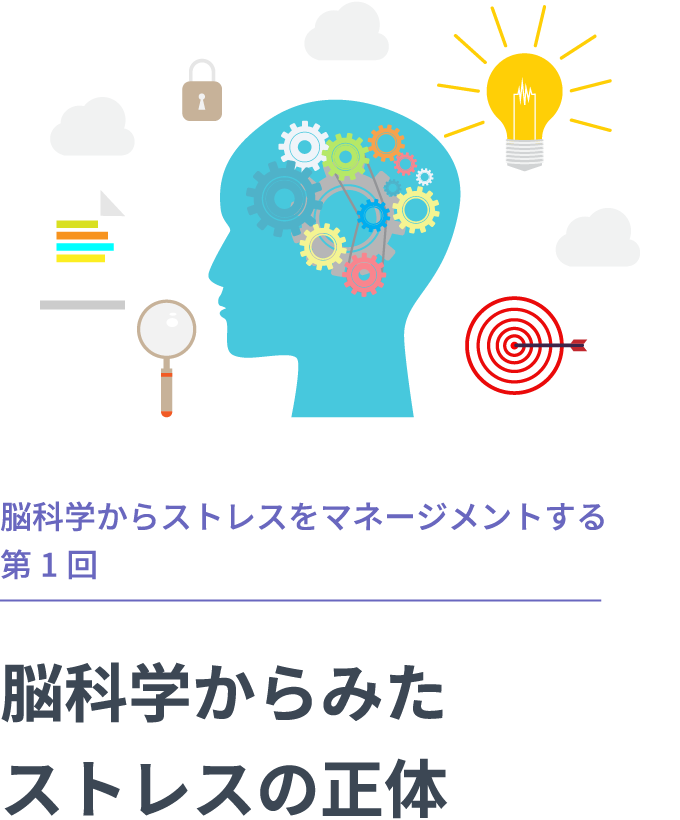
「予測する」という脳の習慣を上手に利用すれば、ストレスを回避できる
そもそも「ストレス」とは何でしょう? ストレスとは、外部からの刺激を受けたときに生じる緊張状態のことを指します。(厚生労働省「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス」より)
では、その「緊張状態」とはどういうことなのでしょうか? 「心の問題」として語られることも多いメンタル疾患ですが、その要因となるストレスの正体とは? そして、そのストレスをどう自分で対処していけば良いのでしょうか?
こちらのコラムでは、毎月、作業療法士である菅原洋平氏に、脳科学と臨床に基づいたお話しを伺っていきます。今回は、脳科学からみたストレスと、その対処法についてお聞きしました。

菅原洋平(すがわら・ようへい)
1978年、青森県生まれ、静岡県育ち。作業療法士。ユークロニア株式会社代表。国際医療福祉大学卒業後、作業療法士免許取得。民間病院精神科勤務後、国立病院機構にて脳のリハビリテーションに従事する。その後、脳の機能を活かした人材開発を行うビジネスプランをもとにしたユークロニア株式会社を設立。現在はベスリクリニックで外来を担当する傍ら、全国講演も精力的に行う。著書に『あなたの人生を変える睡眠の法則』(自由国民社)、『「疲れない」が毎日続く!休み方マネジメント』(河出書房新社)など多数
「ストレスがある状態」と「ストレスがない状態」を、脳の仕組みから理解する
皆さんが日常的によく使う「ストレス」という言葉ですが、このストレスとは何か、脳科学の分野から説明しましょう。
脳は自分が不測の事態に陥ったとき、頭を働かせてすぐに行動に移せるよう、次の行動を「予測」し、行動させる器官です。自分の身に次に何が起こるか予測できない状況の場合、心拍数を高めて血圧を上昇させ、呼吸を早めて準備状態を作ります。
例えば、これまで一度も会ったことがない人と初めて会う場合、緊張しますよね。心臓がドキドキする経験は誰にでもあると思いますが、これは相手がどういう人なのか予測できる要素が少ないため、どのような事態が起こっても対応できるようにと脳が反応し、心拍数を上げて準備をしているのです。
しかし、範囲外のことがたくさん重なると、準備が追いつきません。この状態のことを一般的に「緊張している」とか、「ストレスがある」、「ストレスを感じる」などという言い方をします。
逆に、次に何が起こるか予測の範囲内に置かれていれば、心拍数などを上げたりする必要がなく、そういった準備をしなくてすみます。この状態のことを、一般的に「ストレスがない」と言います。
脳の予測に対し、体の感覚データを調整しているのが自律神経
ストレスを理解するには「自律神経」という神経の働きを知る必要がありますので、ここでもう少し専門的なお話をしましょう。
脳が予測したことに対し、代謝を上げ下げして心拍数などの調整をしているのが自律神経です。自律神経の役割は、暑いとか寒いとか痛いなど、体のあらゆる感覚データを脳に集めて、脳の指令を体に伝えることである、と考えると理解しやすいかもしれません。
感覚データを脳に集めて中枢に伝える神経を「求心性精神」と呼び、感覚データを集めて命令する神経を「遠心性神経」と呼んでいます。この集めたり命令したりする神経が自律神経です。
脳は、大量のエネルギー消費を抑えるために予測する
ではなぜ、脳は出来事を「予測」するのでしょうか。それは、脳は非常に燃費の悪い臓器だからです。自分の身に予測していない突発的なことが起こり、いきなり対応しなければいけない場合、たくさんのエネルギーが消費され、脳は疲労します。ですからなるべく想定内の出来事が起こるように予測を立て、エネルギー消費量を抑えているのです。
また、新しい行動も脳に多くのエネルギーが必要になるため、いつもと同じように行動し、新しい行動をとらないよう、脳は戦略をとっています。これが私たちの習慣の仕組みです。
予測できる状況を作り、ストレスをコントロールする
ストレスは、脳が関係しているということがここまでの説明で理解できたと思います。では、日常生活の中で、自分でできるストレス対処法はあるのでしょうか。
例えば、会社で初めての面談をする機会があったとします。その日の朝、作ったことのない朝食づくりに挑戦してみたり、新しい服や新しい靴を履いたりしたりして、気合を入れたくなるかもしれません。
しかし、普段とは違う行動は脳が予測できない範囲を増やし、新しく対応しなければならないことにエネルギーを取られてしまいます。初めての面談のような予測が立ちにくいシチュエーションの場合は、いつもの朝食を食べ、いつもの服装で出かけるなど、できるだけ脳の負担を減らしてあげましょう。
また、仕事や家事のタスクがたくさんあるのに、なかなか取りかかれず、ストレスがたまると感じている人も多いのではないでしょうか。実はやるべきことを先延ばしにすると、脳は疲労するのです。
「あれをやらなきゃ」と思い出すたび、脳はこの頭に浮かんだことを「今はやらない」と制御しなければなりません。制御するのにエネルギーが必要になりますので、脳は疲れてしまうのです。
例えば仕事の打ち合わせが終わり、次に資料をつくる作業に移る際、新しい行動をするためには脳に負担がかかり、「面倒くさいから先延ばしにしよう」という気持ちが生まれます。
これを防ぐには、動作の区切りを意識してみましょう。例えば1つの仕事が終わったら、次にやるべきことに少しだけ手を付けておくのです。脳に次の作業を少しでも見せて準備させておくと、作業を再開する際、スムーズに体に命令することができます。
脳は予測する内蔵であり、予測ができているとストレス反応を起こしにくく、予測ができてないとストレス反応が起こりやすいという仕組みがあります。この法則に従うことで、ストレスはある程度自分でコントロールできるのです。
構成:吉田明乎
企業情報
株式会社Yume Cloud Japan
本社
〒992-0119 山形県米沢市アルカディア1-808-46
山形大学有機材料システム事業創出センター内
Tokyo Office
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1
茅場町一丁目平和ビル8F
FinGATE KAYABA
Yume Cloud Inc.
440 North Wolfe Road, Sunnyvale, CA 94085