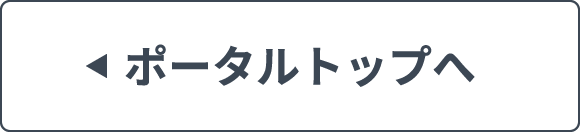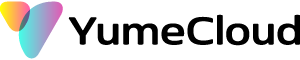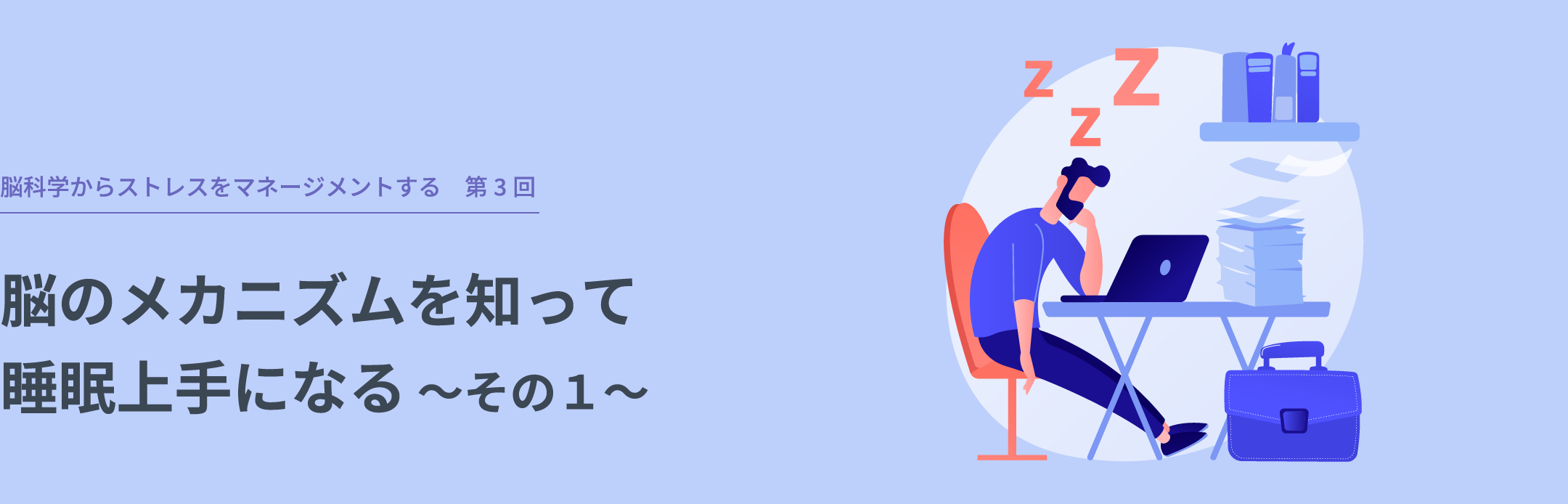
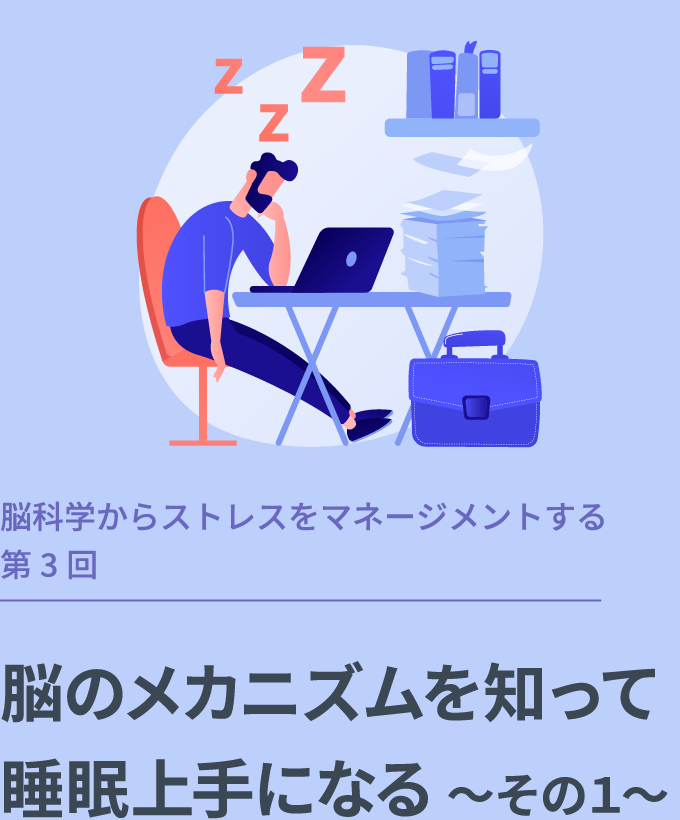
『日本人の5人に1人はなんらかの睡眠負債(不足)を抱えていると言われています。
睡眠はストレスと深く関わっており無視できない課題です。そこで今回は睡眠についてお聞きしました。
とても興味深い内容ですのでシリーズでお伝えしていきたいと思います。

菅原洋平(すがわら・ようへい)
1978年、青森県生まれ、静岡県育ち。作業療法士。ユークロニア株式会社代表。国際医療福祉大学卒業後、作業療法士免許取得。民間病院精神科勤務後、国立病院機構にて脳のリハビリテーションに従事する。その後、脳の機能を活かした人材開発を行うビジネスプランをもとにしたユークロニア株式会社を設立。現在はベスリクリニックで外来を担当する傍ら、全国講演も精力的に行う。著書に『あなたの人生を変える睡眠の法則』(自由国民社)、『「疲れない」が毎日続く!休み方マネジメント』(河出書房新社)など多数
あなたの睡眠は、脳にとって“よい睡眠”?
2つチェックしていただきたいことがあります。まず1つ目。目が覚めて4時間後の状態をチェックしてみて下さい。もし眠くなったり集中できなかったりしたら、睡眠が量的に足りないか、質が悪いかのどちらかが考えられます。これは脳が一番よく働くのは、目覚めて4時間後で最もパフォーマンスが発揮されなければならない時間帯だからです。
もう1つは、おやすみ前に“眠気”が来ているかどうかです。睡眠とは、もともと睡眠欲求があってのこと。眠りたいから眠るのであって、眠らなければいけないから眠るわけではありません。多くの方は、寝る時間が来たから寝るといった具合に、眠気がなく就寝時間を迎えています。本来は、脳に溜まった睡眠物質が脳内に入り込んで眠気を作っていきます。溜まった眠気が、質の高い睡眠の条件でもあります。眠気がなくても眠ることはできてしまいますが、そうすると質の悪い睡眠になり、寝起きが悪くなったりします。まずは、この2ポイントをチェックしてみてください。
自分にとっての“眠気”のサインを見つける
睡眠には段階があります。あくびが出て眠いと感じるのが眠気ですが、実は、あくびが出るのはかなり遅い段階です。眠気はもっと早くから出てきています。
例えばテレビを観ているのに気が散るとか、他のことが気になること、ありませんか? キャスターの癖が気になってニュースが頭に入ってこないとか。本筋とは違うことが気になり、自分が焦点を当てるべきところに当てていない、目がキョロキョロ動いてしまう様な状態のとき、これをマイクロサッケードと呼び、この時から既に眠気は始まっています。仕事中や車の運転中にも起きます。トラックの運転手さんなどは、このマイクロサッケードという現象を知っておくことが安全衛生面で非常に重要です。知っていれば自分の眠気に気づくことができ、事故を防げます。
マイクロサッケードを放置しておくと、次はマイクロスリープという2〜7秒の非常に短い睡眠が起こります。会議や打ち合わせの最中「あ、今、聞いていませんでした」みたいなことありますよね? 聞いていたはずなのに、ちょっとの隙があって「あれ?」となる。これがマイクロスリープという現象で、寝ていたという自覚はないけれど、エラーが起きている。読書中に同じ文章を2度読み返したり、パソコンのミスタッチを2、3度繰り返したり、思っていることと違うことを口走ったり……。けれど、それが“眠気”であると気づいていないことが多いのです。
この後さらに放置しておくと、アクションスリップという、言っている(思っている)こととやっていることが違う、という現象が起こります。ものを落とすなど、他人にもわかるちょっとしたミスです。それでもまだ、これが“眠気”だと気づいていないことは多く、脳が「いよいよまずいぞ」と判断すると、覚醒させるために顎の筋肉を使うあくびが出てくるわけです。眠気にはこれだけの段階があります。早い段階で気づいて睡眠に入ることができれば、寝起きもよくなる。自分で睡眠を誘導できます。自分にとっての“眠気”のサインを見つけることから始めてみるのが、いいでしょう。
すぐに眠れない状況での“眠気”対処法──計画仮眠
睡眠のリズムが整っている人は、大抵同じような時間帯に眠気が出てきます。なので、「この後の打ち合わせでは、意識が飛んでしまうようなことが起きるな」と、予測が出来て計画仮眠を取ることができます。目を閉じてもらえれば脳波は変わりますので1分程度目を閉じるだけでもスッキリした感はあり、マイクロスリープが出てくることは防げます。ある程度自分の行動を客観的に観察してみると「大体午後のこの時間帯に意識が飛ぶな」というのが分かるので、まだ全然眠くなくても、その時間帯の前に1〜5分程度目を閉じるとスッキリ感が得られます。
6〜15分程度目を閉じて仮眠できれば、実際に睡眠物質が分解されて作業効率が上がります。デスクなどで、隙を見てやってみていただければと思います。計画仮眠をすることによって夜の寝落ちを防ぎ夜間の睡眠に入れれば、それを充実させることができます。長期的に時間を見て先に手を打っておくことが、生体リズムをつかさどるコツになります。
寝落ちすると、睡眠の質は悪くなる
寝落ちという現象は、“眠気に気づいていない”ということです。本当はもっと早くから眠気はきているはずなのです。眠気というのは生物にとってリスクがあることなんですね。寝ている間に襲われたら大変ですから。なので、まだそこに刺激や、情報を得られる可能性があったりする場合には、できるだけ眠気を感じなくさせるマスキング能力があるため、眠気を感じないままテレビを観ていたりすると寝落ちをするんです。眠くないまま寝落ちをするということは、眠気を感知できていないので、睡眠を取ろうという欲求もないし、睡眠に向けて身体の準備もできていない。具体的に言うと、心拍数が高いまま最初の睡眠に入るので、睡眠中に下がるはずの代謝率が下がらないまま睡眠をとってしまい、結果、質の悪い睡眠になってしまいます。
次回は、睡眠と生体リズムのお話です。生体リズムの仕組みがわかれば二度寝もOK!?
構成:村上美香
企業情報
株式会社Yume Cloud Japan
本社
〒992-0119 山形県米沢市アルカディア1-808-46
山形大学有機材料システム事業創出センター内
Tokyo Office
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1
茅場町一丁目平和ビル8F
FinGATE KAYABA
Yume Cloud Inc.
440 North Wolfe Road, Sunnyvale, CA 94085